サッカーのオフシーズンは一般的には冬から春にかけてです。
プロもリーグ戦は12月に終わりますし、
高校サッカーは選手権が終われば基本的にはシーズンオフとなります。
基本的にオフシーズンに激しいトレーニングを積み、インシーズンはコンディショニングをしながら試合を重ねていきます。
オフシーズンは大きな大会もなく、トレーニングの強度を上げて身体やメンタルを鍛えるには十分な機会です。
そのオフシーズンのトレーニングの効果を倍以上にする方法を解説していきます。
具体的な内容は
- 期分け
- フィジカルチェック
- フィジカルトレーニング
- 栄養
です。
基本的なことではないか?
と言ったことを感じるかもしれませんがこれが大事です。
以下に解説します。
目次
期分け

期分けとは、シーズンをいくつかの期間に分けて、トレーニング目的を明確にしながら合理的にトレーニングを進める方法です。
一般的にシーズンは、オフシーズン・プレシーズン・インシーズンと3つのシーズンに期分けをします。
オフシーズンでは、基礎体力づくり、およびサッカーに重要な運動能力の向上とともに、スキルの習得を重要視します。
プレシーズンでは、主に戦術面でのチームづくり、さらにフィジカル的には試合における専門的な動きづくりを重要視します。
この時期、練習試合やチーム内の紅白戦がたくさん組まれ、チームづくりの達成度を評価していきます。
他の学校と試合を行うと、フィジカルの差がどの程度あるかわかって課題が見えてきますね。
オフシーズンとプレシーズンで自分の体をケアできるように教育しておくことも重要です。
強度が上がり疲労が蓄積した中で自分をケアできない選手は、シーズン後半に怪我をしてしまう可能性が高いからです。
ここからインシーズンに入っていきます。
フィジカルチェック

オフシーズンに行う、フィジカルチェックの目的は、第1に、現在その選手の持つ基礎体力や運動能力が、どれくらいであるかを客観的な指標で把握することです。
第2に、万が一、ケガによって戦列を離れてしまった場合のリハビリテーショ
ンおよびリコンディショニングを行うときの比較資料としても使えます。
例えば、一度低下した基礎体力や運動能力が、どれくらい回復したかを再確認するために利用したり、競技復帰の目安にしたりするときに用います。
第3に、サッカーに必要な基礎体力や運動能力が、ある期間のトレーニングにおいて、どの程度変化したかを客観的に把握することです。
フィジカルトレーニング

フィジカルトレーニングは、その領域を大まかに分類して、トレーニングの内容を整理しながら進めると、やりやすいと思われます。
フィジカル領域をスキル系・パワー系・スタミナ系に分類して目的を明確にして、それぞれのタイミングを計りながらトレーニングを進めていくことが大切です。
以下にそれぞれまとめます。
スキル系トレーニング
基礎的コーディネーションから専門的コーディネーション、そしてアジリティ・クイックネストレーニングへと移行します。
パワー系トレーニング
基礎的筋力から機能的筋力、さらに高強度のプライオメトリックトレーニングへと移行し、最終的にオーバースピードトレーニングなどに代表されるアシステッドトレーニングを実施できるようにしていきます。
スタミナ系トレーニング
有酸素性持久力の向上を目的としたトレーニングから徐々にスピードアップして、最終的には無酸素性持久力やスピード持久力向上のためのインターバルトレーニングへと移行します。
特にサッカーは間欠的な持久性が求められるため、競技特性に合わせたスタミナトレーニングを意識すると良いでしょう。
私は20秒ダッシュし20秒休むHIITなども用いたりします。
トレーニングの注意点
トレーニングの詰め込みすぎで選手がオーバートレーニングに陥ってしまわないよう注意します。
シーズンを通じて体重や心拍数、疲労の度合いなど日々選手のコンディションを確認しながらトレーニングを進めるように心がけます。
また、フィジカルトレーニングだけがひとり歩きしてしまわないように、常に監督やスタッフとコミュニケーションをとります。
技術・戦術トレーニングの量と強度をみて、バランスをとりながらトレーニングを行う必要があります。
オフシーズンはただ闇雲に行っても効果がありません。
しっかりとしたスケジュールを立てて、チェック→アクションといったサイクルで行えるように心がけましょう。
参考になれば嬉しいです。

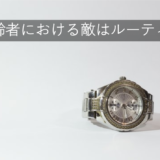

コメントを残す