高齢者の転倒についてシステマティックレビューをまとめました。
 なぜ転ぶ?高齢者の転倒に影響がある因子は?【システマティックレビュー】
なぜ転ぶ?高齢者の転倒に影響がある因子は?【システマティックレビュー】
今回は転倒予防のための介入は具体的にどのように行うか解説したいと思います。
- 転倒リスクの高い高齢者を対象としている
- 転倒予防に関して詳しく知りたい
運動介入は
- 筋力トレーニング
- バランストレーニング
- 認知機能トレーニング
- 二重課題トレーニング
- グループエクササイズ
などが挙げられます。
これらの中から抜粋して紹介したいと思います。
目次
筋力トレーニング
これまでに報告された転倒予防の介入の研究から、どのような高齢者でも同じ内容のトレーニングで同じような予防結果が得られるのではないとされています。
トレーニングには個別性があるので個人個人で要因が違うので行うべきトレーニングも変わってきます。
介護予防や転倒予防のためのグループエクササイズはポピュレーションアプローチとして行っていく必要がありますが、やはり個別で行う介入は欠かせないですね。
負荷や頻度
Csapoらのシステマティックレビュー1)によると、
高齢者に対して筋力向上や骨格筋量増加を目標にレジスタンストレーニングを行う場合、1RM(repetition maximum)の70~80%の高負荷であっても1RMの40~50%程度の低負荷であってもその効果には差が無い
とまとめられています。
また、低負荷量であっても量を十分に担保することによって、骨格筋機能を向上させる効果が期待できるとされています。
内容
座位で行う膝伸展運動や足踏み運動,起立運動,立位での踵上げやランジ運動が勧められています 2 )。
バランストレーニング
バランストレーニングは一般的に行われているトレーニングでありますが、今一度再考してみましょう。
ただ何となくバランスの練習をするのではなく段階的に目的をもって行うことが重要です。
Shumway-Cookの文献によると3)
- 外乱への反応的バランスに用いられる筋応答の組織化
- バランスに必要な感覚入力の組織化
- 二重課題によるトレーニング
が挙げられています。
①は座位や立位で徒手的な外乱を加える課題を中心とし,外乱方向やスピード,大きさに変化を与えて,姿勢の調節やステップ反応を引き出していきます。
バランスを崩した場合「姿勢制御」を行う必要があります。
支持基底面から出た重心を保つにはステップして支持基底面を広げたり移動させるか、姿勢の調節をして支持基底面内に戻す必要があります。
そのための姿勢調節の練習やステッピング反応の練習を行います。
②は立位が安定した状態で環境の変化による反応や予測からバランスを保つ課題とし,開眼・閉眼での立位練習や床面を変えバランス練習を行っていきます。
環境の変化に対応できるように床面の環境を変えて行います。
屋外を歩く場合には平坦でなく不整地も歩く必要があります。
傾斜や柔らかい床(バランスクッションなど)で立位練習を行い足部からの感覚入力を賦活していきます。
私はよく靴下を脱いでもらい裸足で行ってもらうこともあります。
③は二重の認知課題を加えバランスや動作練習を行っていきます。
二重課題は 動作 + 認知課題 を行うということです。
二重課題能力が低下している高齢者は転倒が多いといわれているためこの能力を練習することが重要です。
例えば計算課題をしながら歩いたりボールをつきながら歩いたりといった練習を行っていきます。
バランスはこれらの要素に合わせて段階的に行うことが望ましいとされています。
以上高齢者の転倒予防の運動介入についてまとめました。
臨床の参考になれば嬉しいです。
参考資料
1)Csapo1 R, Alegre LM. Effects of resistance training with moderate vs heavy loads on muscle mass and strength in the elderly: A meta-analysis. J Med Sci Sports, 2016, 26, p.995–1006.
2)島田裕之. 高齢者理学療法. 医歯薬出版株式会社, 2017, p.398-399.
3)Shumway-Cook A, Woollacott MH. モーターコントロール-研究室から臨床実践へ-. 医歯薬出版株式会社, 2013, p.321.
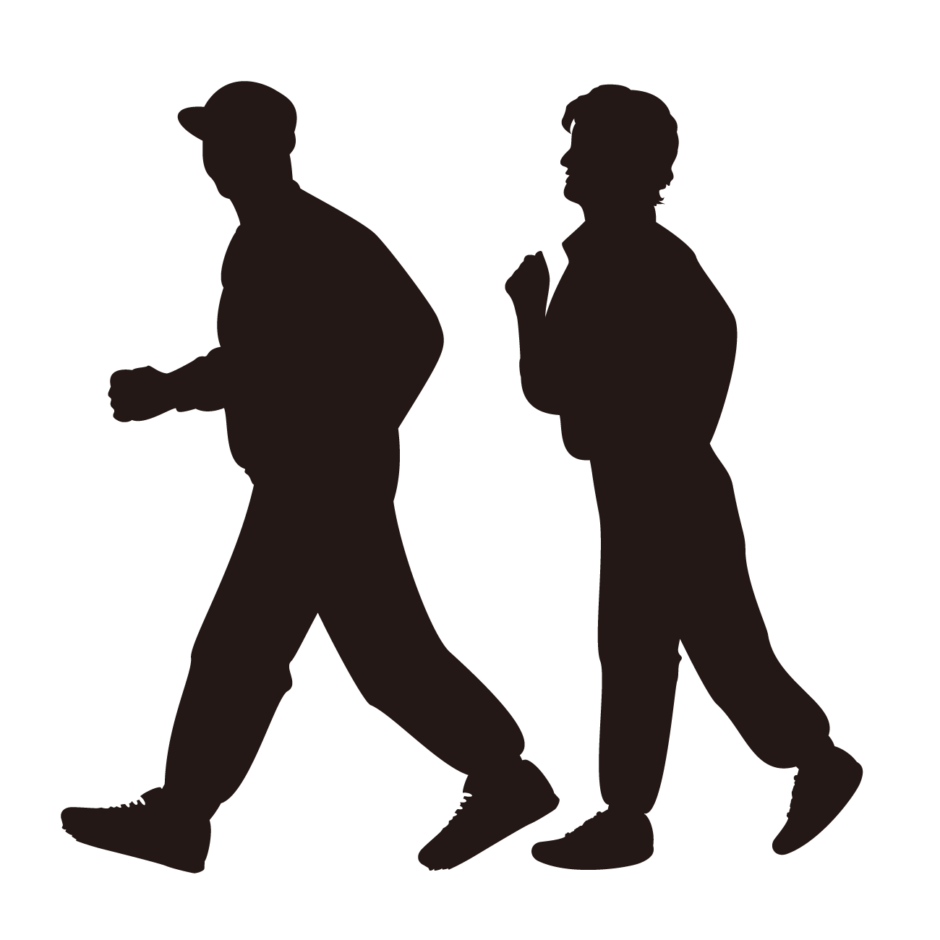


コメントを残す